 トップページ
トップページ ×
×
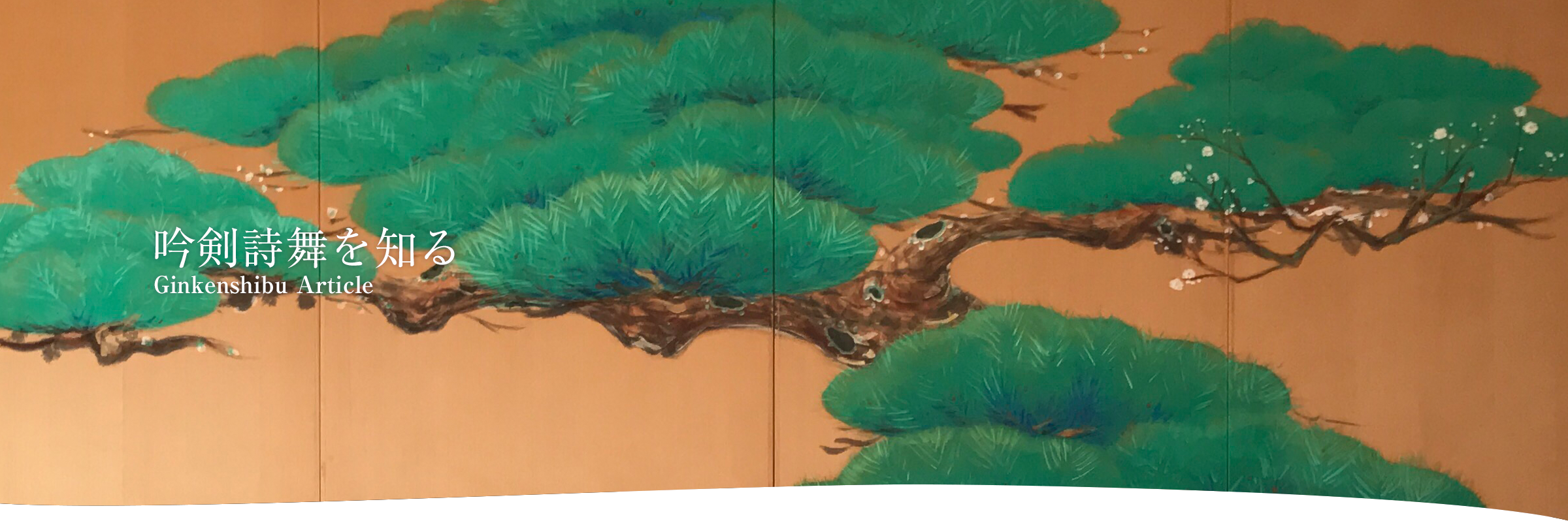

杜甫「春望」
(とほ「しゅんぼう」)
漢詩は学ぶほどにその魅力にとりつかれ、味わい深くなります。
毎回何首かの詩を取り上げ、奥深く豊かな詩の世界を少しだけ解きほぐしてみたいと思います。
出来る限りテレビやラジオの演目に合わせて詩を選びますので、吟詠の一助にお読みいただければ幸いです。ときには和歌も取り上げたいと思います。
唐の玄宗皇帝の治世は、その前半は年号にちなんで「開元の治」とたたえられる理想的な政治が行われ、経済的にも文化的にも最高潮に達します。が、治世の後半、楊貴妃を得てからは政治を顧みず、安禄山の乱を誘発します。この乱によって経済も社会も大打撃を受け、唐王朝は次第に衰退へと向かうことになります。この乱の時期に活躍したのが、杜甫や李白の盛唐の詩人たちです。
西暦七五五年十一月、幽州(今の北京)を護っていた安禄山が謀反をおこし、十二月に洛陽を陥れます。翌七五六年六月、潼関が破られると、玄宗皇帝は蜀へ亡命し、太子亨が霊武で即位し、ついで鳳翔へと進出します。杜甫は新帝肅宗即位の報を聞いて、単身その行在所へと赴きますが、途中、賊軍に捕らえられ、長安に幽閉されます。翌七五七年、四十六歳の杜甫は長安にあって「春望」を作ります。「春望」は、春のながめ、の意。
國破山河在[国に破れて山河在り]
城春草木深[城春にして草木深し]
感時花濺淚[時に感じては花にも涙を濺ぎ]
恨别鳥驚心[別れを恨んでは鳥にも心を驚かす]
烽火連三月[烽火三月に連なり]
家書抵萬金[家書万金に抵る]
白頭搔更短[白頭搔けば更に短く]
渾欲不勝簪[渾て簪に勝へざらんと欲す]
<国都長安は破壊されたが、山や川は変わらずもとのようにある。荒れた町にも春がやってきて、草や木が深々と生い茂っている。この時世に感じては、楽しくなるはずの花を見ても涙がこぼれ、家族との別れを悲しんでは、慰められるはずの鳥の声にも心を驚かされる。戦火は三か月もの長い間続いている。家族からの手紙は来ない、来れば万金にあたいするほど貴重だ。心痛で白くなった髪の毛は、掻けばかくほど薄くなり、まったく冠をとめる簪を支えられなくなりそうだ。>
前半は、山河や花鳥に代表される自然と、人間社会のことがら=人事とを対比します。永遠に変わらぬ自然と、絶えず変遷する人事、そして自然の美しさによって、戦争のむなしさや別れの悲しさ、人の世の無常を詠います。
首聯(第一句・第二句)は、松尾芭蕉『奥の細道』の平泉の条に引用されています。
さても、義臣すぐってこの城にこもり、功名一時の叢となる。
「国破れて山河あり、城春にして草青みたり」と、笠うち敷きて、時の移るまで涙を落としはべりぬ。
夏草や兵どもが夢の跡
芭蕉は奥の細道の旅に杜甫の詩集を携えていたといいます。青を連想する「草木深し」をずばり「草青みたり」と言って、「叢」や「夏草」を印象づけます。さらに笠をうち敷いて草の上に座り、涙を流します。
「家書万金に抵る」は、お金で売り買いできないものを、お金に換算する言い方です。家族からの手紙は来ない、だからもし来れば大金に相当する、と。宋の時代の蘇軾は、時間をお金に換算して
言います。「春宵一刻値千金」。春の夜の一刻は千金にも相当するほど貴重だ、と。「千金」も「万金」も実数を言うのではありません。
杜甫の詩の後半は、もう自然は詠わず、人事だけを詠います。しかも、戦争という「公」と、家族との別れという「私」とに分けて、第五句から第八句まで、公→私、私→公と構成します。最後の第八句は、白髪が「短」くなったと、一見「私」のようですが、もう冠はかぶれない、という「公」の内容です。
第七句で「白頭搔けば更に短く」と言います。頭を掻くのは、なすすべがないことを表します。「短」は、長短という長さをいうのではなく、多少あるいは濃淡などの量をいいます。当時の官僚は髪の毛を結い上げて冠をかぶり、冠が傾かないように簪をさしていました。簪にたえられないとは、冠をかぶることができないこと、そして自分はもう官僚にはなれない、という絶望的な思いを表します。
杜甫は「私」を詠うだけではなく、「公」の人として、その思いを詠った詩人です。皇帝を補佐して、堯や瞬の時代の理想の社会を実現させたいという志をいだいていたからです。が、その志は遂げられませんでした。