 トップページ
トップページ ×
×
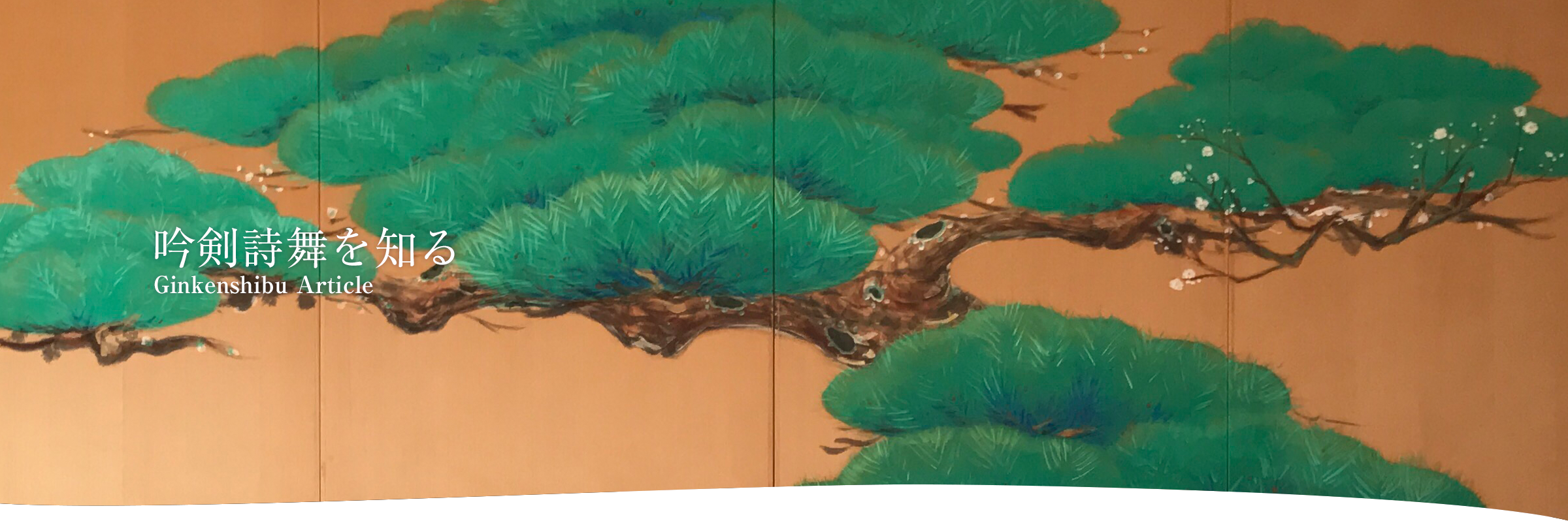

盧綸「長安春望」
(ろりん 「ちょうあんしゅんぼう」)
漢詩は学ぶほどにその魅力にとりつかれ、味わい深くなります。
毎回何首かの詩を取り上げ、奥深く豊かな詩の世界を少しだけ解きほぐしてみたいと思います。
出来る限りテレビやラジオの演目に合わせて詩を選びますので、吟詠の一助にお読みいただければ幸いです。ときには和歌も取り上げたいと思います。
盧綸は蒲(山西省永済県)の人で、大暦年間(七六六~七七九)
しばしば科挙の試験を受けますが、及第しませんでした。詩は七言律詩で、科挙に及第できない孤独と懊悩が詠われています。
東風吹雨過靑山[東風雨を吹いて青山を過ぐ]
却望千門草色閑[却って千門を望めば草色閑なり]
家在夢中何日到[家は夢中に在って何の日にか到らん]
春來江上幾人還[春は江上に来って幾人か還る]
川原繚繞浮雲外[川原繚繞たり浮う雲の外]
宮闕參差落照閒[宮闕参差たり落照の間]
誰念爲儒逢世難[誰か念はん儒と為って世難に逢ひ]
獨將衰髩客秦關[独り衰髩を将って秦関に客たらんとは]
<春風が雨を吹いて青い山を通り過ぎてゆく。振りかえって宮城のたくさんの門を望むと、若草がのどかに繁っている。故郷の家は夢にみるだけで、いつ帰れることか。春は川のほとりにかえってきたが、人はいったい幾人故郷に帰ったことか。川原は浮き雲のむこうまでうねうね続き、宮殿は高くあるいは低く夕陽に照らされている。儒者となって世の苦難に逢い、髪が白くなってもひとり長安に旅する身でいようとは思いもしなかった。>
作者は城市の近くの山を歩いているようです。青い草の萌えだした山では雨まじりの風が吹き、「千門」のあたりでは雨にぬれた「春の草」が風に揺れています。川も見えます。川岸から視線を遠くにはなつと、雲の向こうまで草原が続いています。
この連載の第12回でも紹介しましたが、「春の草」は別れの悲しみをさそう詩語です。「春草」「芳草」「細草」ともいいます。出典は『楚辞』の「招隠士」。
王孫遊びて帰らず/春草生じて萋萋たり
春が再びかえってきて若草が繁っているのに、親しい人は旅に出たまま帰らない、と。そこで春の草を見ると「別れの悲しみ」がイメージされ、旅にある人は若草を見ると、故郷に帰りたい、と望郷のおもいにかられます。
『楚辞』の「萋萋」はさかんに茂るさまです。この盧綸の詩では「草色閑」と言います。「閑」は、のどか。若草がいたずらに茂っていることを言います。第三句・四句は「春の草」を承け、「家は夢中に在って何れの日にか到らん/春は江上に来って幾人か還る」と、科挙に及第して家に帰りたいのに及第できないでいる、今年はいったい何人帰ったことか、と憂いに沈みます。
この詩では「門」が「千門」「宮闕」「秦関」と三つ詠われます。たくさんの門、宮城の門、秦の地方の関所、です。宮城のたくさんの門から宮殿、そして都長安のある地域へと、その範囲が広がっていくことが分かります。目線が、身近な風景から、浮雲の向こうの原野へと移り、さらに広く長安の町を含む地域を詠うことによって、故郷には帰れず長安での生活が長いこと、孤独であることをいいます。「門」に視線が注がれるのは、科挙に及第してその門の中に入りたい、という願望の表われなのでしょう。
第六句目の「落照」は夕陽です。夕方には雨がやんだようです。夕焼けに映える宮城は、美しいけれども、なんともやるせない気持ちがただよいます。そこで、思うようにならない生活で髪も白くなり、この地にさすらうようになろうとは思いもしなかった、と、自嘲ぎみに結びます。「客」は旅人。故郷を離れている人は「客」という意識をつねにもっていました。
第七句目の「儒」は儒者です。当時の儒者は古代に理想の政治を行った暁と瞬の世を再び実現させるべく天子を補佐する、という志をもっていました。しかし「世難」に逢ってそれもかなわない、と。「世難」は、七六三年チベット軍が長安に侵入し戦乱の世になったことも指すのでしょう。盧綸は七四八年(一説に七三七年)の生まれですから、チベット軍の侵入は十六歳のときです。「衰髩」は、世の混乱を経験し、科挙にも及第できない憂い悲しみの大きさ深さを表しています。
第一句「青山」の青、第六句「落照」の赤、第八句「衰髩」の白が、詩のアクセントになっています。