 トップページ
トップページ ×
×
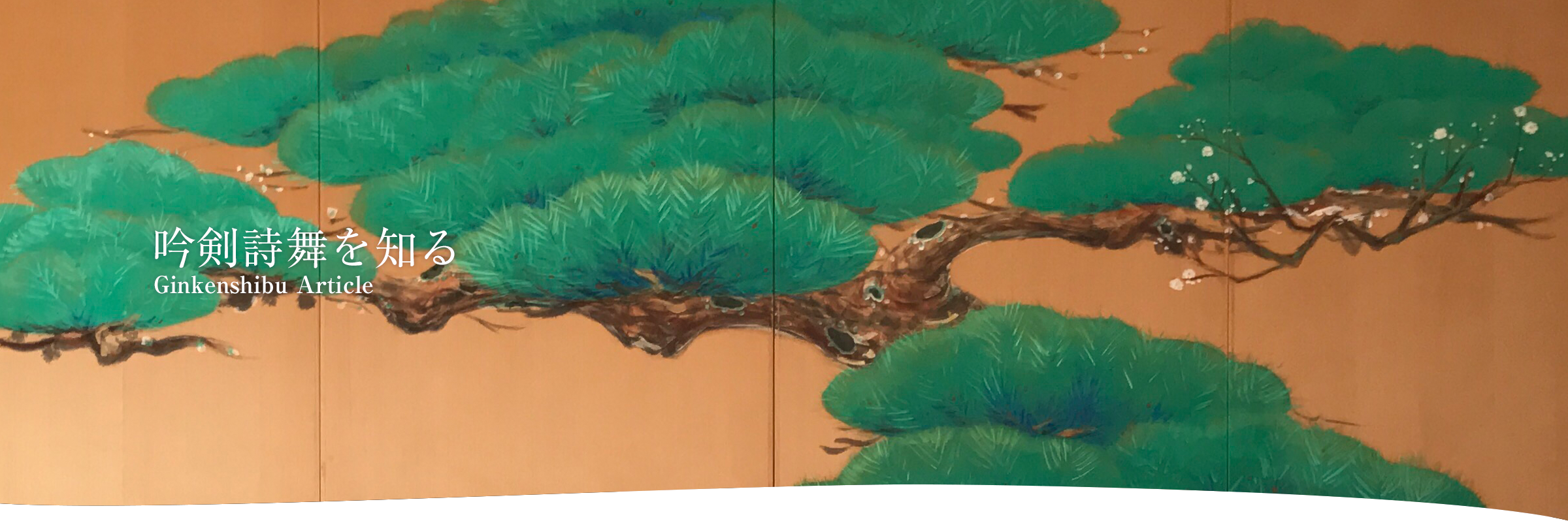
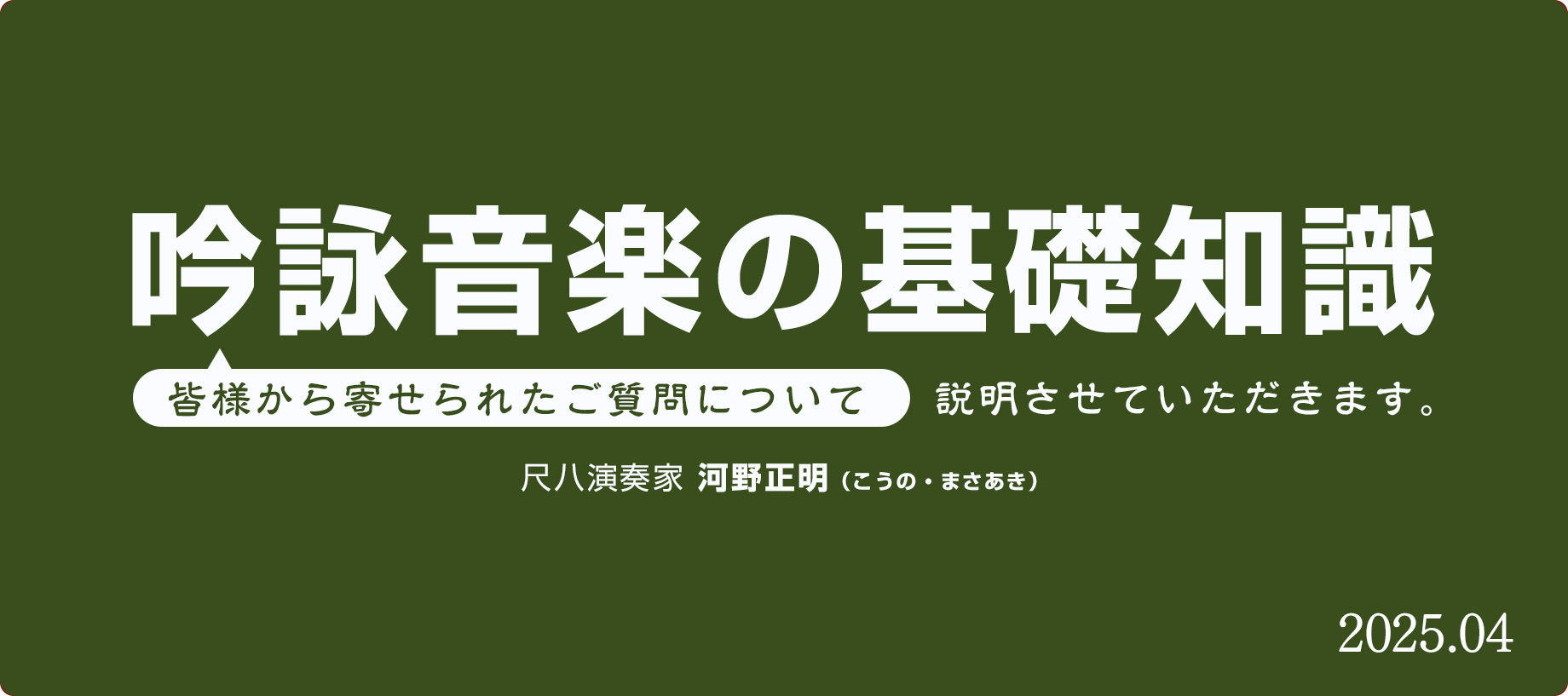
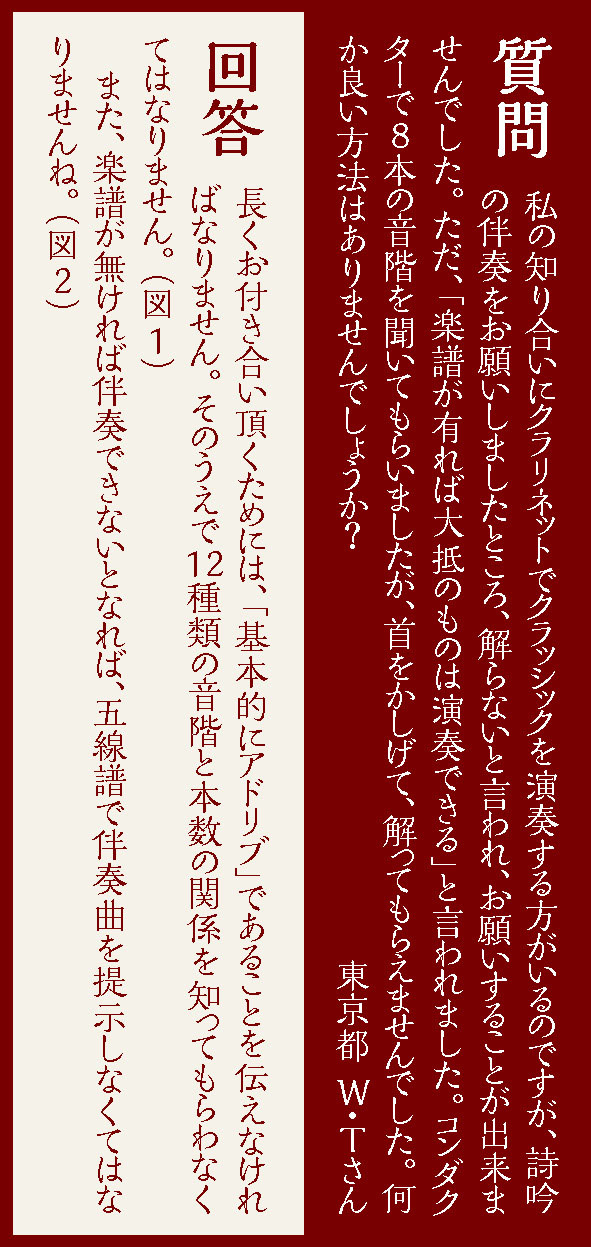

〈説明〉
クラリネットは詩吟の伴奏には何の不自由もなく対応できる楽器です。尺八の場合、一尺八寸管で演奏できるのは、水二本(十一本)、一本、四本、六本の4種類の本数しか演奏できません。二本調子の時は、一尺七寸管に持ち替えなくてはならないのです。その点クラリネットはピアノのように本数に関係なく自由に演奏できます。勿論、その為にはある程度の技量は必要とします。また尺八の場合は最低音から最高音まで約24律。つまり2オクターブしかないので、コンダクターのように最低音を「ミ」最高音も「ミ」として演奏するためには長さの違う尺八を12種類必要とします。これはほとんどの演奏家が持ち合わせておりません。つまり一尺八寸管で4種類の本数の演奏はできても六本調子以外は間に合わせの演奏ということなのです。なぜなら、低音部が不足の為、他の音で代用することになるからです。その点クラリネットは最低音から最高音までの幅が80律、つまり4オクターブ弱ありますから、何本調子でもコンダクターと同じかそれ以上の幅をもって演奏できるのです。最低音がE(低い8本)最高音が4オクターブ弱上のC(4本)まで使えます。高音は初心者には難しいとのことですがとにかく、尺八やフルートより圧倒的に広い音域をもっています。
クラッシック音楽の畑の方でも、アドリブに対応できる方と、譜面の無い演奏は苦手という人とがいます。普段の演奏活動によってその技量は異なります。巷で流れている歌や音楽を聴いただけでそのメロディーを即座に再生して演奏できる人は詩吟を聞いただけで同じメロディーを演奏できます。しかし、どうしても譜面が無いと……と言う方の為に、ひな形という意味で一曲示せば、他の吟題の時も参考になるでしょうし、また本数と調性との関係を示しておけば、他の本数に変換することも容易でしょうから、ここに一例を示しておきましょう。
※こちらの質問は『吟と舞』2021年3月号に寄せられたものです