 トップページ
トップページ ×
×
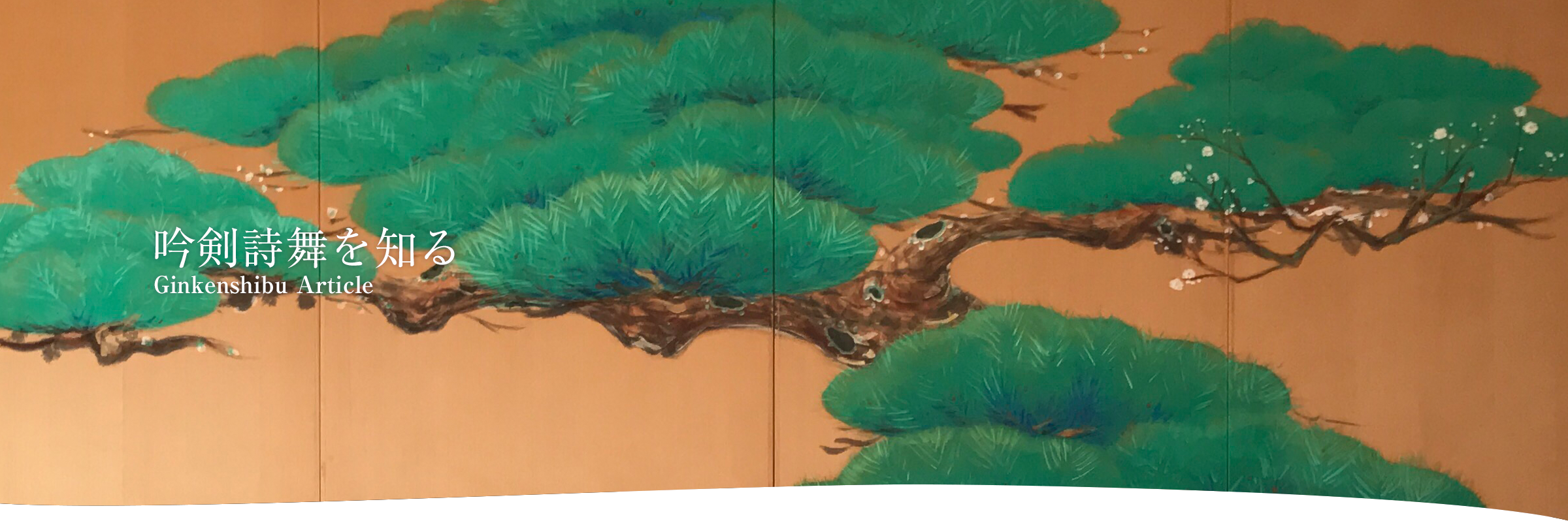

朱熹「酔うて祝融峰を下る」
朱熹(一一三〇~一二〇〇)は南宋の儒学者で、字は元晦または仲晦、号を晦庵と言います。「朱子学」の朱子です。「子」は先生という意味です。
唐代までの学問は字句の解釈を研究する「訓詁の学」でしたが、宋代になると、程明道・程伊川・張南軒などの学者が、形而上学という新しい学問を展開しました。朱熹(朱子)はそれを集大成し、孔子・孟子の儒学に組織と体系を与え、老荘仏教を超える理気心性の学を樹立しました。そこで宋代の学問を「朱子学」と言います。時には道学・性理学・理学・程朱学とも言います。
この学問は人と社会を平和にすることを目指しています。簡単に言うと、人は宇宙の理(道理)のもとに存在していて、その理に支えられて人にはみなそれぞれ性(本性)がある、それを「性即理」と言う、人はその性と理を損なうことなく、仁義礼知信孝などの徳を体得実践して、平和と幸せを実現させなければならない、となります。
朱熹は、三十八歳の秋、長沙(湖南省)衡山の北麓の下、岳麓書院に張南軒を訪ね、学を窮めようと切磋琢磨しました。約二か月の滞在が終わろうとする十一月初旬、衡山七十二峰の最高峰、祝融峰(海抜一二六六メートル)に登り、その時の感動を詩に詠いました。それが「醉下祝融峰」(酔うて祝融峰を下る)です。
我來萬里駕長風[我来って万里長風に駕す]
絶壑層雲許盪胸[絶壑の層雲許く胸を盪かす]
濁酒三杯豪氣發[濁酒三杯豪気発]
朗吟飛下祝融峰[朗吟飛び下る祝融峰]
〈私は万里の道のりを長風に乗って祝融峰までやって来た。深い谷に雲がモクモク湧くのを目の当たりにすると、感動で胸が震える。濁り酒を三杯飲むと、たちまち豪快な気分になり、高らかに詩を吟じながら、飛ぶように祝融峰を下って来た。〉
「長風」はどこまでも吹きわたる風。「駕」は乗る。「層雲」は幾重にも重なる雲。「許」はこんなにも。「盪」はゆすぶる、の意です。
漢詩は自分のことを詠う詩ですから、短い詩形で「我」と言うことはほとんどありません。それだけに、最初に「我来たる」とあると、祝融峰にやってきた嬉しさが強く伝わってきます。 「我来」の下の五字「万里駕長風」は、右の訳では、長風に乗ってやって来たと、来るときの状況を言っているという解釈です。が、もう一つ別の解釈があります。それは「我来たる」、頂上にやって来て、どのような気分になったかを下の五字で言っている、という解釈です。つまり〈私は祝融峰の頂上にやって来た。すると心はまるで長風に乗って万里かなたまで飛んで行けそうな気がする〉と。
前者の風に乗ってやって来た、という解釈は「我駕長風万里来(我長風に駕して万里を来たる)」と言うのを、やって来た感動を強調して「我來」と最初に言い、承句・結句と韻を合わせるため語順を入れ替えたと考えれば、何も問題はありません。平仄や韻を合わせるために語順を入れ替えることはよくあります。
承句は、杜甫の「岳を望む」の「胸を盪かして曾雲生ず(盪胸生曾雲)」を踏まえています。杜甫は遠くから東岳泰山を望み見ています。朱熹は、頂上から谷を眺めています。しかも、目の当たりに見ています。そこで「許く」と臨場感を出しています。
男性的なスケールの大きな詩です。起句の峰の頂上で風に吹かれる爽快さ、承句の深い谷に層雲が連なる雄大さ、スケールの大きな光景に促されて転句の濁酒を飲む豪快さ、結句の朗吟しながら峰を飛ぶように駆け下りる壮快さ。起句と結句がうまく照応しているのも巧みです。
朱熹の詩は道学臭がなく、温厚篤実な人柄が自ずから現れています。感動すると何首も続けて詩ができたといいます。詩ばかり作っていると学問に差し障りがあるので、ある時「禁詩」し、詩を作ることを止めました。が、禁詩すると体調が悪くなったので、一日何首までと決め、ついには禁詩の禁も破ってしまったといいます。
