 トップページ
トップページ ×
×
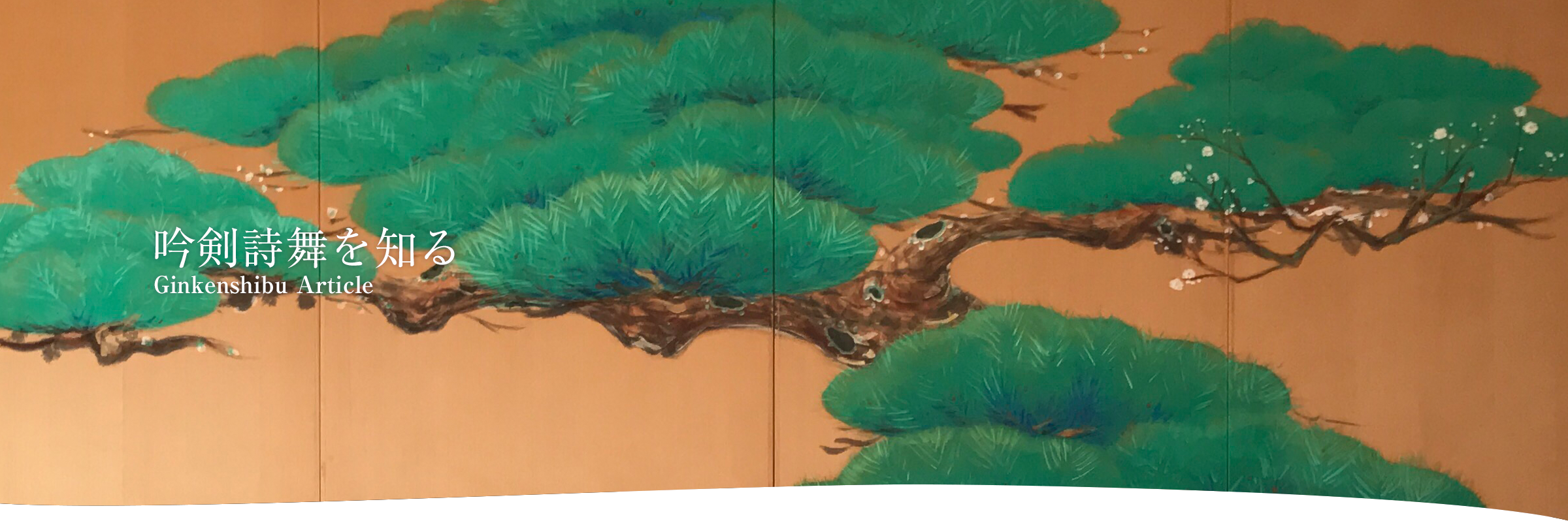

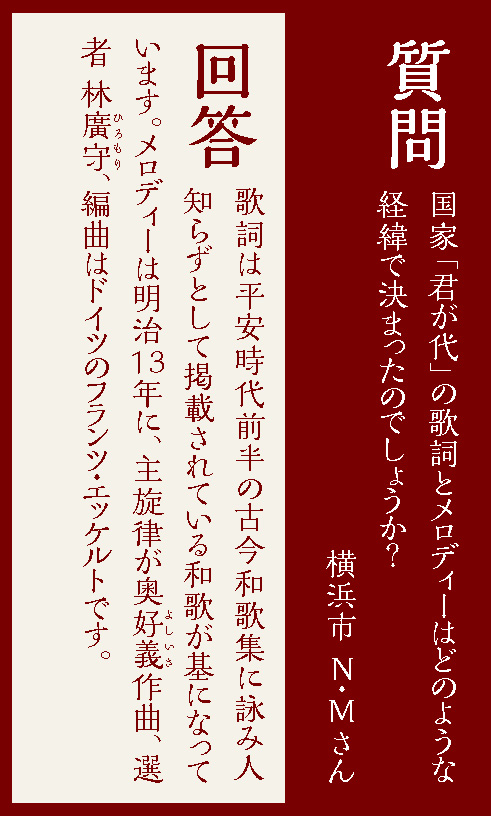

〈説明〉
最初に、これから述べる説明は出典のほとんどがクラウンレコード出版の「君が代の全て」から引用させていただいたものであることを紹介しておきます。
歌詞の基歌は今から千百年以上前の平安時代前半の西暦九〇五年、当時の名歌を集めた古今和歌集(以下『古今集』と略す)の中に「賀」の歌として最初に収められている。
「わが君は 千代に八千代に 細れ石の 巌となりて 苔のむすまで」
この歌の大意は「私の尊敬する貴方の御寿命がいついつまでも続きますように、小石が集まって大きな岩となり、それに苔が生える程まで末永く健やかにおわしませ」と理解してよいでしょう。そしてこの歌が天皇の命による勅撰和歌集である古今集に「詠み人知らず」として冒頭の「賀」の歌に選ばれているということは、選者が発掘してきたのではなく、当時すでによく知られており、しかも作者が分からないほど古くから、いわば民謡のように歌い継がれていた名歌だからこそ、初めての勅撰和歌集に採用されたのでしょう。
この歌がよく知られていたことを示す例として、在位八八四~七年の光孝天皇が僧正遍昭の古希を祝って詠んだ歌に、「斯くしつつ とにもかくにも長らへて 君が八千代に逢ふ由もがな」とある。これは「わが君は 千代に八千代に云々」の歌を基にして詠まれたものと考えられます。つまり八八五年には「わが君は……」の歌がすでにあったということのみならず、これが一般に知れ渡っていたと考えるべきでしょう。
ここで一旦話を変えまして、「細れ石の巌となりて」を不思議に思っている方に説明します。大きな岩が川を下っていく間に細かく砕かれるのは誰しもが納得するところでしょうが、細かくなった小石が何故大きな岩になるのかが理解できない方も多いのではないでしょうか。石灰質の多い地層を通ってくる水には石灰質が溶け込んでいて、長年の間に砂利石がこれらの石灰成分によってコンクリートのように固まってしまう現象があります。石灰質角礫岩と言い、岐阜県の天然記念物とされています。
歌の話に戻ります。
この「わが君は……」の歌が古今集に選ばれたことにより「わが君」の意味が単に個人的に尊敬する相手のことだけでなく、古今集の編纂を命じた今上天皇(醍醐天皇)のことにもかけて意図されているように変わってきたのでしょう。 古今集以前に「わが君は……」が多くの人々に口ずさまれ引用されていたであろうことは想像するしかありませんが、古今集以後は様々なところで使われたり応用されたりしているのが分かります。
平安中期の藤原公任は一〇一五年の和漢朗詠集に、朗詠するにふさわしい「祝」部の名歌として「わが君は……」を挙げている。さらには、平安末期一一八五年の「古今集註」には「わが君は……」の歌について、「この歌ツネニハ〈キミガヨハチヨニヤチヨニ〉トイヘリ」と注記している。つまり、平安の末期には「わが君は」が「君が代は」になっているものが多い。また室町から江戸初期に多く作られた「和歌披講譜」(和歌を雅な調べで披露するための例し歌)の初めか終わりに、必ず「君が代は」の歌を挙げている。江戸時代には一般の庶民もお正月の行事としてお祝いの餅を食べる時、「君が代は」の歌を口の中で唱えながら箸をとった。その様子を詠った歌に「わが春の若水汲みに昼おきて 餅を喰いつつ祝ふ君が代」がある。この時のメロディーは勿論披講譜です。節の紹介は省略します。
現在国歌として歌われているメロディーは明治になってから決まりました。
明治2年7月、英国王子エジンバラ公が来日し天皇陛下に謁見することになった。その為、これに先立って、横浜に駐在していた英国陸軍軍楽隊から日本の国歌の楽譜を要求されたが我が国にはまだ国歌が無かったので急遽作曲することになり、英国軍楽隊長のジョン・ウイリアム・フェントンに作曲してもらうことになった。儀礼式で必ずしも歌詞が必要なわけではないが、行く行くは他の国同様、国民の間で歌われるようにとフェントン氏が考え、歌詞を要求したのでした。しかし国歌としての歌詞が決まっているわけではないので、誰もが知っている和歌「君が代」を渡したのでしょう。切羽詰まった対応です。もしかすると、日本側は「君が代」を歌えるように作曲してもらえば、後から他の和歌に変えても歌えるだろうからという気持ちもあったかもしれません。その証拠に明治11年の天長節には「君が代」と共に他の和歌が同じ伴奏で歌われています。
この初代「君が代」はファンファーレとしては良かったのですが、早いうちから改定が求められておりました。というのもフェントン氏は日本語がほとんどわからず、言葉の運びとメロディーがうまく合わず不自然である点が不評でした。西南の役後、動乱が落ち着いてからフェントン氏に代わって軍楽教師に着任のドイツ人フランツ・エッケルト氏を中心に、宮内省の楽人から募集した作品の中から、今日の「君が代」が生まれました。
※こちらの質問は『吟と舞』2021年2月号に寄せられたものです