 トップページ
トップページ ×
×
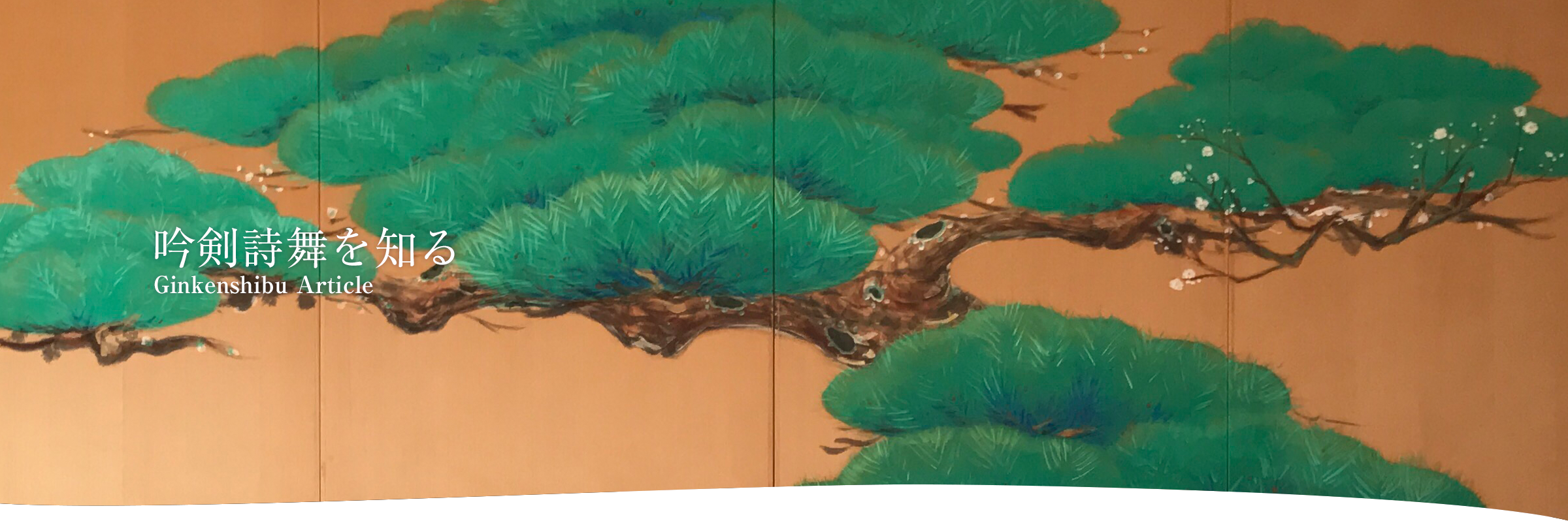

劉禹錫「秋思」
日本には秋の寂しさをしみじみと詠う和歌がたくさんあります。早くは『万葉集』に大伴家持(七一八頃~七八五)が「うつせみの世は常なしと知るものを秋風寒み思ひつるかも」と、秋風の寒さと妻を亡くした悲しみを重ねて詠っています。時代が降ると秋の夕ぐれを詠う「三夕」が『新古今集』秋部に収められます。
寂しさはその色としもなかりけり槇立つ山の秋の夕暮れ(寂蓮)
心なき身にもあはれは知られけり鴫立つ沢の秋の夕暮れ(西行)
見渡せば花も紅葉もなかりけり浦の苫屋の秋の夕暮れ(定家)
秋の気に感じて傷み悲しむ文学を「悲秋文学」と言います。『万葉集』は八世紀頃の成立ですが、中国では紀元前三世紀、戦国時代の宋玉(前二九〇~前二二三)が「九弁」という長編の詩に次のように言っています。
悲哉、秋之爲氣也。蕭瑟兮草木搖落而變衰。
[悲しいかな、秋の気たるや。蕭瑟として草木揺落して変衰す。]
〈なんと悲しいことか、秋の気というものは。寒々と風が吹き、草木は花や葉を揺らぎ落とし、形を変えながら衰えていく。〉
宋玉は天子の補佐をしてよりよい社会を実現させたいと望んでいました。が、誰にも認められず、追放され、秋風の中をさすらいました。秋は悲しいと言うのは、失意不遇という自らの境遇の表象でもあったのです。
その後、紀元前二世紀、前漢の武帝が「秋風の辞」を作り、物が移り変わり衰えるように青春も忽ち過ぎて老いがやってくる、と季節の秋と人生の秋とを重ねてその悲しみを詠います。結びは次の有名な句です。
歡樂極兮哀情多。少壯幾時兮奈老何。
[歓楽極まりて哀情多し。少壮幾時ぞ老いを奈何にせん。]
〈歓び楽しみが極まってくると、かえって哀しい気持ちが増してくる。この少壮の楽しい時はいつまで続くのだろうか、やがてやってくる老いをどうしたらよいのだろう。〉
唐代の杜甫(七一二~七七〇)は、官職に就けない時期に「九日」の詩で「老い去きて悲秋強ひて自ら寛うす」と「悲秋」を詠い、家族全員を引き連れ食糧を求めて旅をしているとき、「登高」で「万里悲秋常に客と作る」と詠っています。そして長江沿いの夔州で宋玉を思って詠います。
搖落深知宋玉悲[揺落して深く知る宋玉の悲しみ]
風流儒雅亦我師[風流儒雅また我が師なり]
〈草木の揺落する季節にあって宋玉の悲秋の思いが切々と胸に迫る。宋玉が風流にして儒雅という高い精神の持ち主であったことにおいてもまた私の師と仰ぐ人である。〉
こうした伝統的な悲秋文学の流れに異を唱えたのが、今回の劉禹錫(七七二~八四二)の「秋思」です。
自古逢秋悲寂寥[古より秋に逢うて寂寥を悲しむ]
我言秋日勝春朝[我は言う秋日春朝に勝ると]
晴空一鶴排雲上[晴空一鶴雲を排して上る]
便引詩情到碧霄[便ち詩情を引いて碧霄に到る]
〈昔から秋になると人はその寂しさに悲しくなるが、私は秋の日なかのほうが春の朝に勝っていると言いたい。晴れた空に一羽の鶴が雲を押し分けて上ると、私の詩心もそれに誘われて碧い大空の上までのぼるのだ。〉
碧く抜けるような高い空に、白い鶴が雲の上まで翔けてゆく姿は、気品があり優雅です。春の朝の浮き立つ気分とは違います。
詩は、作者の境遇やその時々の心の状態によって詠い方が違ってきます。晋の陶潜(三六五~四二七)は「飲酒」の詩の中で「菊を采る東籬の下、悠然として南山を見る」に続けて、秋の夕暮れを次のように詠っています。
山氣日夕佳[山気日夕に佳く]
飛鳥相共歸[飛鳥相共に帰る]
陶潜から六百年ほど後の清少納言は、『枕の草子』第一段で陶潜と同じ風景を次のように言います。
秋は夕暮。夕日のさして、山の端いと近うなりたるに、烏の寝どころへ行くとて、三つ四つ、二つ三つなど、飛び急ぐさへあはれなり。まいて、雁などのつらねたるがいと小さく見ゆるは、いとをかし。日入り果てて、風の音、虫の音など、はた言ふべきにあらず。
清少納言はもとより政治にはかかわっていません。陶潜は政界から逃れて隠棲していました。
