 トップページ
トップページ ×
×
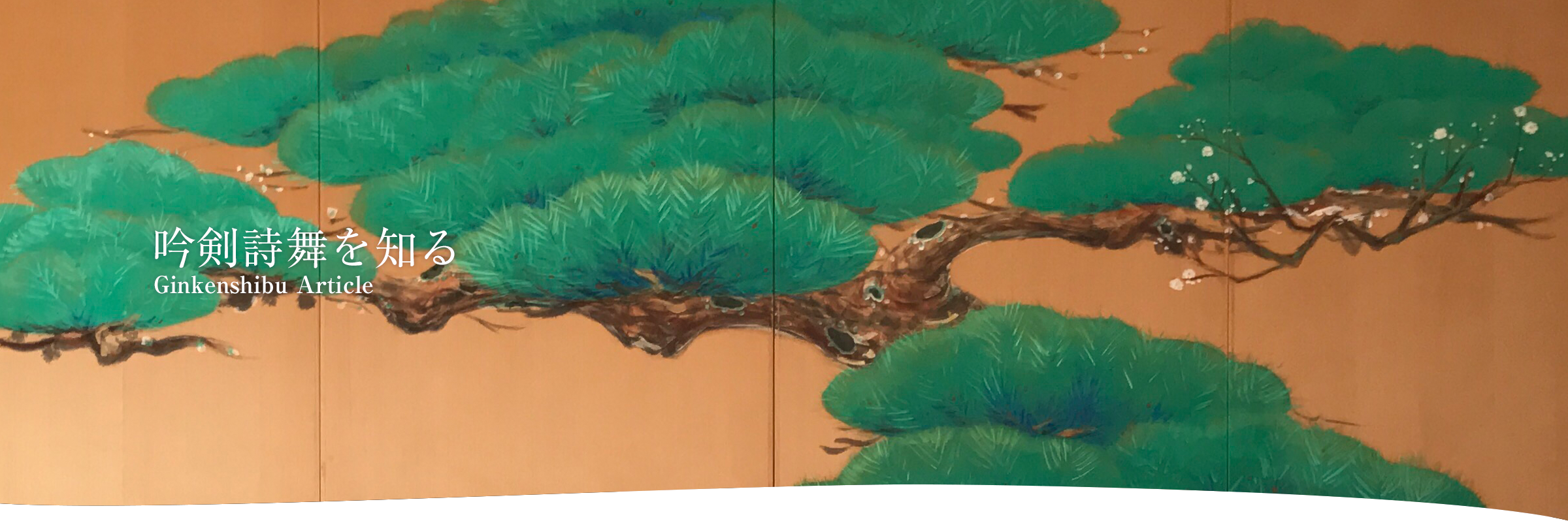

梁川星巖「一の谷懐古」
今回も一の谷の戦いの詩を読みます。作者は、江戸時代の梁川星巌(一七八九~一八五八)です。古戦場に立ち、昔の凄惨な戦いに思いを馳せます。
二十餘春夢一空[二十余春夢一空]
豪華吹散海𤲬風[豪華吹散海𤲬の風]
山排殺氣參差出[山は殺気を排して参差として出で]
潮迸冤聲日夜東[潮は冤声を迸らせて日夜東す]
憶昔滿宮悲去鷁[憶う昔満宮去鷁を悲しみ]
欲將往事問飛鴻[往事を将って飛鴻に問わんと欲す]
斕斑剩見英雄血[斕斑剰し見る英雄の血]
塹樹鵑啼朶朶紅[塹樹鵑啼いて朶朶紅なり]
〈平家二十余年の春は夢のように儚く消えさり、海からの風に栄耀栄華も吹き尽くされてしまった。いま、山々は殺気を押し分けるかのように靄を拝して高くあるいは低く突き出て、荒波は平家の人々の怨みを込めるかのように日夜都のある東へと流れている。船に乗って逃れた安徳天皇の御心はいかばかりであったろうか、宮人がみな悲しんだように、私も昔を想い、空高く飛ぶ鴻に往事のことを尋ねてみる。ここで流された英雄たちの鮮血は夥しかったに違いない。塁の跡と思われるあたりには、杜鵑が血を吐いて染めた真赤な花が枝もたわわに咲いている。〉
前半は、驕れる平家の栄華が春の夜の夢のように儚く消え去り、一の谷の古戦場に立ちこめる靄は殺気をこめるように山すそに漂い、海の荒れる波に平家の怨みがこもっているようだと言います。後半は、一の谷の戦いに敗走した安徳天皇や宮人に思いを馳せ、往事の様子を空飛ぶ鴻に尋ねます。鴻は塁のあった方へ飛んで行きます。するとそこには、多くの兵士の血に染められたように真赤な花が咲いています。血を吐きながら鳴くという杜鵑も鋭く鳴いて悲しんでいます。
一の谷の戦いの後、屋島の戦い、壇の浦の戦いがあり、安徳天皇は祖母二位の尼に抱かれて海中の長生殿に赴かれましたが(本連載第50回)、第五句の「憶う昔満宮去鷁を悲しみ」は、詩題が「一の谷懐古」ですから、一の谷の戦いに敗れて安徳天皇が船に乗って屋島に逃れることを言います。「鷁」は龍頭鷁首の船、天子(天皇)の御座船を言います。
鵯越の奇襲のあと館に火がかけられ、宮人は慌てふためいて船に乗りこみます。その様子はどうだったのでしょうか。松尾芭蕉(一六四四~一六九四)はこの古戦場を訪れて『笈の小文』に次のように往事を想像しています。
その代のみだれ、その時のさわぎ、さながらに心に浮び、俤につどひて、二位の尼君、皇子をいだき奉り、女院の御裳裾に御足もつれ、舟屋形にまろび入らせたまふ御有様、内侍・局・女嬬・曹子のたぐひ、さまざまの御調度もてあつかひ、琵琶・琴なんど、褥・蒲団にくるみて船中に投げ入れ、供御はこぼれて鱗の餌となり、櫛笥は乱れて海士の捨て草となりつつ、千歳の悲しびこの浦にとどまり、白波の音にさへ愁多くはべるぞや。
『平家物語』では、逃れた雑兵が船に取りつくと、身分ある人が優先と、太刀や長刀で腕をうち切られ肘をうち落とされ、渚に倒れ伏して呻き叫ぶ声夥しく、海に沈んだ者は数知れず、陸にさらした首の数は二千余、一の谷の小笹の原の緑の色も血に染まって薄紅になった、と言います(巻九「平家海上に浮かばるる事」)。
詩中の「海𤲬」は海岸。「𤲬」は水のほとり。「斕斑」は美しいさま。「剰し見る」は「ただ見る」の意です。梁川星巌は歴史を題材として詠う「詠史」を得意としていました。
