 トップページ
トップページ ×
×
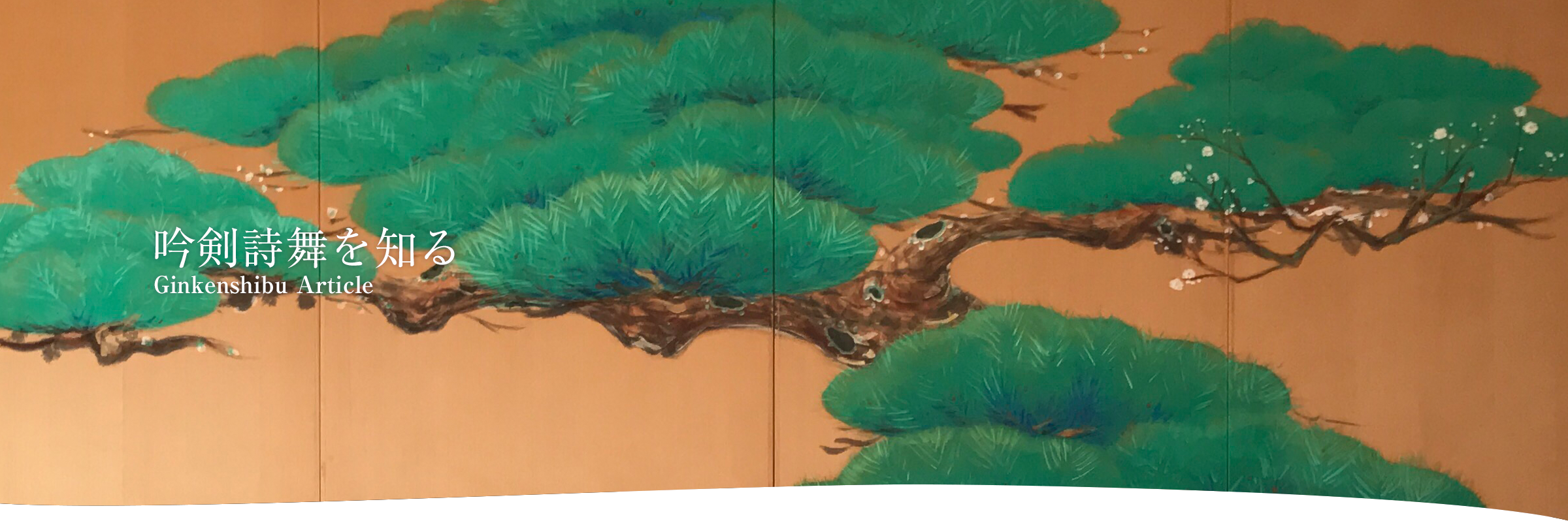

松口月城「青葉の笛」
「青葉の笛」は『平家物語』の哀しい物語に基づいています。
平清盛の死後、勢いを得た源氏方の木曽義仲(義経の従兄弟)が北陸から京の都に迫ると、平家は幼い安徳天皇と三種の神器を擁して都を脱出し、義仲と義経の源氏どうしが戦っている間に、一の谷(現在の神戸市須磨区)に城郭を構えて再起を図ります。
寿永三年二月七日(一一八四年三月二十日)、義経は義仲を破ると一の谷へ軍勢を進めます。正面から兄の範頼が攻撃し、義経は搦手すなわち側面から攻撃をしかけます。一の谷の城郭の背後は三十丈の懸崖、十五丈の絶壁、そこから攻めてくるはずはないと平家の警護は手薄でした。義経は、鹿が越せるなら同じ四つ足の馬も越せるはずと、卯の刻(午前六時頃)断崖を馬で攻め下り、一騎当千の勇士もそれにつづきます。有名な鵯越の逆落としです。この奇襲が功を奏して、平家の軍は敗走し、須磨の浦に浮かべた船に乗って屋島へと落ちのびて行きます。
この戦いで、平家の公達は忠度・知章・敦盛を始め十人討ち死にします。それぞれの逸話が語られるなかで、「笛」は「敦盛最期」の件に出てきます。
熊谷次郎直実が手柄を立てようと待っていると、豪華な模様の着物に薄緑色の鎧を着け、黄金色の太刀を差した武者が、白馬に乗って沖の船に向かっています。敵に背中を見せるとは臆病者と、直実が扇を挙げて招くと、武者がとって返してきます。渚に上がるところを、駒の頭を向けなおすが早いか、直実は組み伏せて左右の膝で鎧の袖をむずと押さえて「首を掻かん」と兜とを取ります。見れば自分の息子小次郎と同じ年ごろ。薄化粧に鉄漿をしています。
これは侍ではない、平家の公達だ。自分が息子を思うようにこの子の父親も心配しているだろう、気の毒だ。「名のらせ給へ。助けまゐらせん」と申すと、「なんぢはいかなる者ぞ」と問い返します。直実が名のると、「なんぢがためにはよい敵ごさんなれ。なんぢに合うては名のるまじきぞ。首実検のあらんとき、やすく知られんずるぞ。急ぎ首を取れ」と言います。
直実は、あっぱれなことだ、今討たなくても、源氏が負けることはない、お助け申したい、と言います。が、後ろを見ると味方の兵が迫って来ています。いま私がお助けしても、あなたは逃れることなく討たれてしまうでしょう。ならば私が討って、死後のご供養をいたしましょう、と首を切ったのでした。
首を包もうとして鎧直垂をといてみると、笛が錦の袋に入っています。直実はこれを見て、「いとほしや。今朝、城のうちに管弦し給ひしは、この君にてましましけるにこそ。何としても、上臈は優にやさしかりけるものを」と哀しみます。この若者が敦盛で、生年十七歳、笛は鳥羽の院より賜った「小枝」という名品でした。
子を思う親の情愛と若い命を取らなければならない哀しさ、敦盛の優雅と風流、矜持と潔い最期。『平家物語』屈指の名場面です。
一谷軍營遂不支[一の谷の軍営遂に支えず]
平家末路使人悲[平家の末路人をして悲しましむ]
戰雲收處有殘月[戦雲収まる処残月有り]
塞上笛哀吹者誰[塞上笛は哀し吹し者は誰ぞ]
〈一の谷の合戦で平家の軍勢は源氏に押されて、けっきょく支えきれずに敗走してしまった。平家の末路を思うと人々を悲しませないではおかない。戦いが終わったとき明けの空には残月がかかっていた。早暁、平家の陣営から哀調を帯びた笛の音が聞こえていたが、いったい誰が吹いていたのだろうか。(まさしく敦盛が吹いていたのだ。)〉
転句の「残月」は『平家物語』にはありません。文部省唱歌(明治十九年・一九〇六)の 「青葉の笛」では「一の谷の軍破れ/討たれし平家の公達あわれ/暁寒き須磨の嵐に/聞こえしはこれか青葉の笛」とあります。「青葉の笛」という言い方は、芸能から出た伝承とされています。
松口月城(一八八七~一九八一)は福岡県那珂川の人。開業医として医療に従事するかたわら、吟詠漢詩家として活躍し、書道や南画にも多彩な才能を発揮しました。
