 トップページ
トップページ ×
×
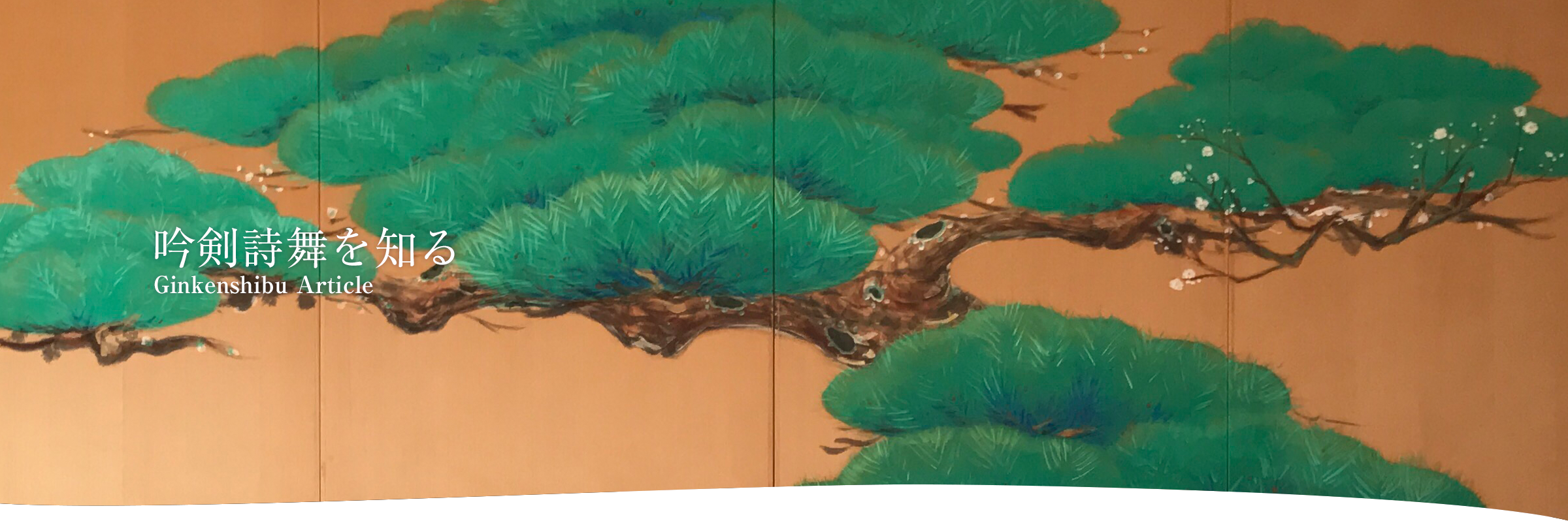
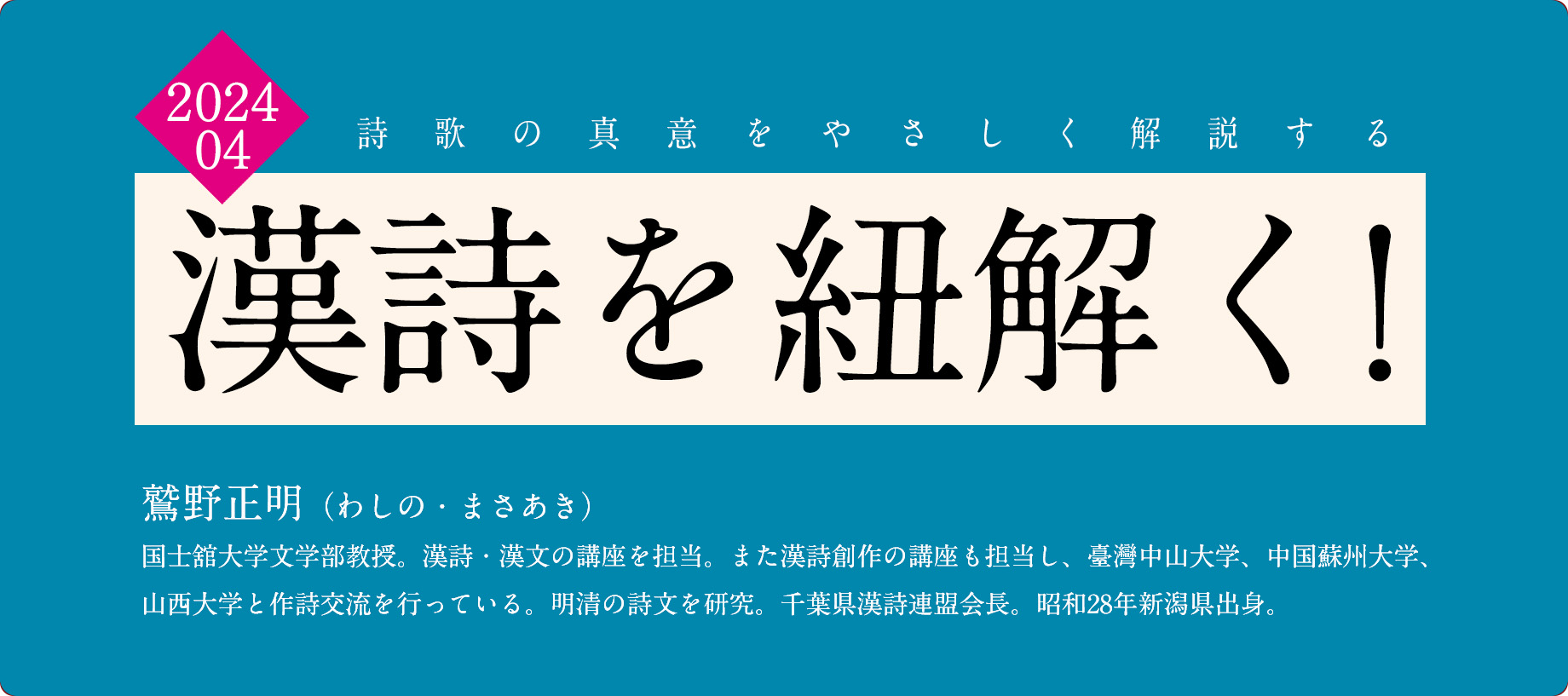
李益「夜受降城に上って笛を聞く」
「受降城」は漢の武帝の時に、将軍公孫敖が匈奴の降伏を受けるために初めて塞外に築いた塞です。唐代になると、突厥の侵入を防ぐために、神竜三年(七〇七)、朔方軍総管張仁愿が黄河の北側にそれぞれ四百里(約二二四キロ)離れて東・中・西の三つの受降城を築き、首尾相応じて突厥の南寇の路を絶ったといいます(『旧唐書』九十三「張仁愿伝」)。唐代では、東受降城は勝州の北八里、中受降城は大同城西北五百里、西受降城は豊州の西北八十里にあったといいます。この詩の受降城は、そのどこであるかは諸説あって確定できません。中受降城とする説が多いようにも思われますが、近年では西受降城(内蒙古自治区杭錦後旗烏加河の北岸)とする説もあります。
李益(七四八~八二七)は大暦九年(七七四)から十年ほど従軍しています。この詩の制作年は確定できませんが、「往々鞍馬の間に文を為り、槊を横たえて詩を賦す」(『唐才子伝』巻四)というように、従軍のおりに作った作品です。王昌齡や李白にも劣らない、中唐期の七言絶句の絶唱と評されています。
囘樂峯前沙似雪[回楽峰前沙雪に似たり]
受降城外月如霜[受降城外月霜の如し]
不知何處吹蘆管[知らず何れの処にか芦管を吹く]
一夜征人盡望鄕[一夜征人尽く郷を望む]
〈回楽峰の前の砂漠は雪のように白い。受降城の外に月影は霜のように冴えわたる。いったいどこで吹いているのだろう、もの悲しい芦笛の音が聞こえてくる。その音にさそわれて、今夜、兵士たちはみな故郷の空を眺めやるのであった。〉
「回楽峰」は大同の西五百里にある、とも言われます。が、はっきりとは分かりません。「回楽峰」を「回楽烽」に作るテキストもあります。「回楽烽」なら、李益の「暮れに回楽烽を過ぐ」に「烽火高く飛ぶ百尺の楼」とありますので、戦況を知らせる烽火台です。火を扱う烽火台、その前に広がる雪のように白い砂、ということになると、取り合わせの妙が一つ加わります。
この詩は、前半の二句が対句になっています。対句とは、文法的に同じ働きをする言葉が同じ順番で相対している二つの句をいいます。名詞(回楽峰)+名詞(前)+名詞(沙)+助動詞(似)+名詞(雪)名詞(受降城)+名詞(外)+名詞(月)+助動詞(如)+名詞(霜)「前」と「外」はどちらも場所を表します。「雪」と「霜」は類似の語です。「似」は、ここでは「にる」と読んでいますが「ごとし」と読むこともできます。
砂漠は戦場です。砂も月も真っ白で、それを「雪」のようだ、「霜」のようだ、と視覚に訴え、また冷たさを肌身に感じさせるようにして、風景全体を立体的に描きます。冷たい空気がピンと張りつめている、殺伐とした戦場です。白くて寒々としている風景には、人の心の寂しさや悲しさも重ねられています。
前半二句は視覚と触覚に訴えますが、後半は聴覚に訴えます。「芦管」は芦の茎でつくった芦笛です。また一説に胡笳ともいいます。悲しい音色で、望郷をいざないます。たとえば王之渙の「涼州詞」では後半に
羌笛何須怨楊柳[羌笛何ぞ須いん楊柳を怨むを]
春光不度玉門關[春光度らず玉門関]
と詠われ、岑参の「胡笳の歌」では冒頭に
君不聞胡笳聲最悲[君聞かずや胡笳の声最も悲しきを]
紫髥綠眼胡人吹[紫髥緑眼胡人吹く]
吹之一曲猶未了[之を吹いて一曲猶お未だ了らざるに]
愁殺樓蘭征戍兒[愁殺す楼蘭征戍の児]
と詠われています。曲中に別れの歌の「折楊柳」があったら、望郷への思いはますます掻きたてられます。「尽く望む」の「尽」は、一人残らずみな、の意。この一語が効いています。
前半の「回楽峰」と「受降城」をあらためて見ますと、その所在の不確定さを越えて、望郷を掻きたてる象徴として働いていることに気づきます。敵の降伏を受けいれ(受降)、楽しみを回復(回楽)させ、早く故郷にかえりたい、と。