 トップページ
トップページ ×
×
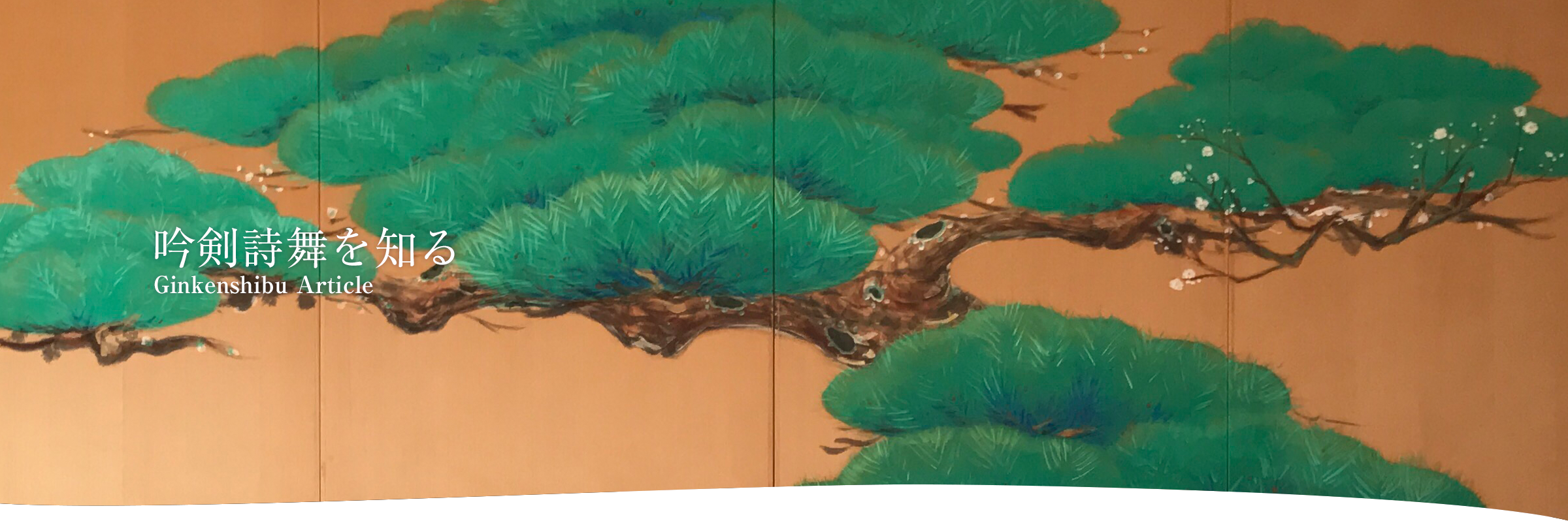

良寛「時に憩う」
良寛(一七五八~一八三一)の詩は第28回で「余生」を読みました。今回は「時に憩う」です。
擔薪下翠岑[薪を担うて翠岑を下る]
翠岑路不平[翠岑路は平らかならず]
時憩長松下[時に憩う長松の下]]
靜聞春禽聲[静かに聞く春禽の声]
<薪を背負って春の山を下る。山の緑は美しいが路は狭くて凸凹している。ときおり高い松の根方で休憩し、小鳥の囀を聞くと静けさがひときわ身にしみる。>
「翠岑」は春の青々とした山。国上山をさします。五言絶句で、二句目と四句目の最後の「平」「声」が押韻されています。薪を集めて山道を歩き、心地よい汗をかき、ちょっと一休み、という素朴で心地よい詩です。漢詩では樵は隠者の象徴です。僧侶ですから修行の一環でもあるでしょう。
良寛も気に入っていたようで、この詩には六種類以上のバリエーションがあります。
よく知られているのは次の詩で、「岑」「尋」「禽」で押韻されています。
擔薪下西岑[薪を担うて西岑を下る]
西岑路難尋[西岑路は尋ね難し]
時憩長松下[時に憩う長松の下]
支頤聽春禽[頤を支えて春禽を聴く]
<薪を背負って西側の険しい路を下る。狭くて凸凹していつしか路に迷ってしまう。そんな時は高い松の根方で休憩し、あごを手で支えて春の小鳥の囀りを聴く。>
前者は、「翠岑」を二度繰り返して緑の美しい山を強調し、結句は静かに鳥の囀りを聞いています。そこで詩全体が落ち着いた静かな感じになります。後者は、「道に迷う」ということから、山道を上ったり下りたりしているようすが想像されます。そして、やれやれとばかりに、松の根方で「支頤」=あごを支え、「聴」=耳を傾けて鳥を聴きます。文字が少し違うだけで詩の印象がかわります。
作務の厳しさや、荷を下ろして休憩しているようすも想像できます。だからでしょうか、「時に憩う」を「時に卸す」としているものもあります。いずれにしても、「鳥鳴いて山更に幽なり」( 王籍)というように、どちらの詩も、鳥が鳴いて山はますます静寂につつまれ、良寛はますます俗世を超越して、自然と一つになって無我の境地に入ってゆきます。
良寛は三十九歳のとき故郷の越後(新潟県)に帰り、寺に入らずに四十歳のとき国上山の五合庵で生活し、四十八歳から五十九歳まで定住します。
五合庵から町に出て乞こ つじき食し、人々から喜捨をうけ、自分が食べる分以上のものは鳥にやったといいます。次のような詩もあります。
城中乞食罷[城中乞食し罷り]
得得擁囊歸[得々として囊を擁して帰る]
歸來知何處[帰来するは知んぬ 何れの処ぞ]]
家在白雲陲[家は白雲の陲りに在り]
<町の中を托鉢し終わり、てくてくと頭陀袋をかかえて帰る。帰ってくるのはどこだろう、白雲のあたり、そこが我が家だ。>
「白雲」は脱俗の象徴です。五合庵には何もないのですが、あるとき乞食して帰ってみると留守中にどろぼうに入られていたという詩もあります(「賊に逢う」)。
また食べ物がまったく無く、「釜中時に魚有り、竈裡屢しば烟無し」と、釜には時に魚が湧き、かまどはしばしば炊事の煙もたたない、という詩もあります。「釜中に魚が湧く」とは貧しくて長い間炊事をしないたとえです。
乞食の途中では子どもたちと隠れん坊をしたり草合わせをしたり、毬つきなどもしました。綺麗な毬を大事にしていました。
袖裏繡毬直大千[袖裏の繍毬直大千]
謂言好手無等匹[謂言らく好手にして等匹無しと]
可中旨趣若相問[可中の旨趣若し相問わば]
一二三四五六七[一二三四五六七]
<たもとの中の手まりは千金の値打ちがある貴重なもの。われこそは無敵の手まりの名手。毬つきの極意をもしおたずねになるなら、教えてしんぜましょう。ひふみよいむな。>
毬つきの極意とは何でしょうか。無になって「毬」のように天と地の間を無限に往来することでしょうか。晩年、貞心尼から毬をもらい、そのお礼に
つきてみよひふみよいむなやここのとを十とをさめて又始まるを
とも歌っています。