 トップページ
トップページ ×
×
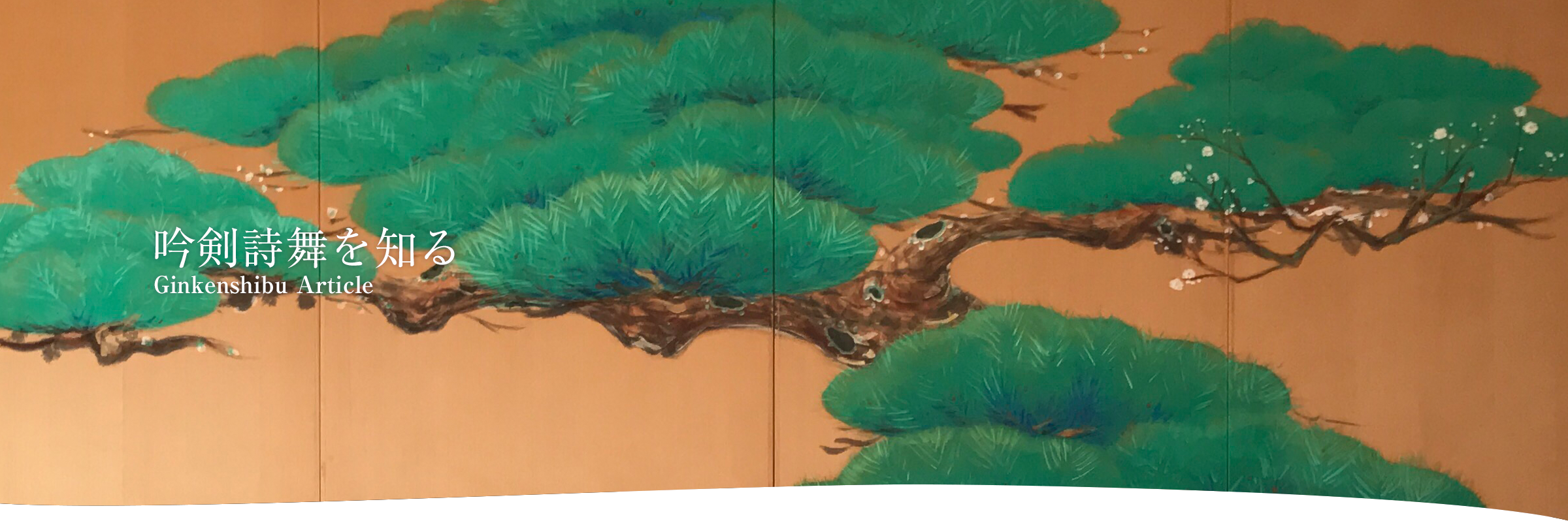

陸游「剣門の道中にて微雨に遇ふ」
(りくゆう「けんもんのどうちゅうにてびうにあふ」)
陸游(一一二五〜一二〇九)は、父の陸宰が朝命を受けて北宋の都汴京(河南省開封)へと急行する船の中で生まれました。その翌年、北宋の天子欽宗と父徽宗は金の国にとらえられ、金の都に連行されます。陸游の一家は戦乱を避け、滎陽(河南省)に仮寓したり、寿春(安徽省)に移ったりして、陸游三歳のときに故郷の山陰(浙江省紹興市)に帰りつきました。欽宗のあとを継いだ弟の高宗は、一一三八年、都を臨安(浙江省杭州市)に定めて、南宋の政権が生まれました。淮河以北は金国が支配し、淮河以南、長江下流を中心とする東南の地域は南宋が支配し、元に滅ぼされるまでの約一五〇年間、金と対峙することになります。
南宋の初め、政界は金と和睦しようという講和派と、あくまでも金と闘い失われた北の半分の地を取り戻そうとする主戦派とが争っていました。陸游は、一一五三年二十九歳のとき、郷里でおこなわれた科挙の最初の試験の解試を受け、講和派の秦檜の孫の塤と首位を争い、第一位で及第します。秦檜は一一四一年、主戦派の岳飛を殺して金と和睦した宰相で、権力を一手に握っていました。一一五四年、陸游三十歳のとき、科挙の次の試験、中央で行われる省試を受験しますが、好成績にもかかわらず、秦檜の妨害によって落第し、秦塤が首位となります。
秦檜が一一五五年に死去し、一一六二年に孝宗が即位すると、陸游は進士出身の資格を得て、枢密院などで働き、やがて四十五歳の一一六九年、夔州通判に任命されます。そして四十八歳の三月、四川宣撫使の王炎に招かれ、興元で幹弁公事兼検法官となり、十一月、成都府安撫司参議官に転じます。
今回読む詩は、興元から四川省の首都成都へ赴任する途中で作られた詩です。「剣門」は山の名前で、四川省剣閣県の北にあり、北方から蜀(四川省)に入る関門でした。左右から絶壁がせまり、門を開き剣をつきたてたように見えることから名づけられたといいます。
剣門道中遇微雨[剣門の道中にて微雨に遇ふ]
衣上征塵雜酒痕[衣上の征塵酒痕を雑ふ]
遠遊無處不消魂[遠遊処として消魂せざるは無し]
此身合是詩人未[此の身合に是れ詩人なるべきや未や]
細雨騎驢入劍門[細雨驢に騎って剣門に入る]
〈ほこりにまみれた旅の衣には酒のしみがまじり、遠く旅をする道中、心をゆさぶられ、感動しない処はなかった。私は、詩人となるべく運命づけられているのだろうか。霧雨の降る中、驢馬にまたがり剣門へと入ってゆく。〉
「征塵」は旅のほこり。「遠遊」は、はるかな旅路。「消魂」は、心の奥を激しく揺さぶること。「合」は「応」と同じ用法で、「まさに~べし」と読みます。当然~のはずだ、の意。「未」は句末につけて疑問を表します。唐の詩人鄭棨は「詩思は覇橋の驢背に在り」と言います。覇橋は長安から東へ旅立つ人の別れの場所でした。驢馬に騎って旅をすると詩心が刺激され詩ができる、というのです。驢馬の背で詩を作った詩人に、李白や李賀などがいます。そこで驢馬といえば詩人というイメージが定着してゆきました。
陸游が詩人となるように運命づけられているのだろうかと自問するのは、心の底に、失われた北半分の地を取り戻すべく働きたいという思いがいつもあったからです。陸游は強硬な主戦論者でした。祖国の回復を願いながらも、願いはかなえられず、風景を見ては詩心がゆすぶられ、霧雨の中を驢馬の背にゆられながら剣門にやってきて、ますます「詩人」となってゆくのです。そこで「これでいいのだろうか」と自ら問うてみたのです。
それにしても起句の「衣上の征塵酒痕を雑ふ」は、それまで歩んできた人生、為す術もなく酒を飲むしかなかった境地を物語る絶妙な句です。詩人として生きる定めのようなものも感じられます。それだけに、自分は詩人として終わる運命なのかという嘆息や、雨のそぼ降る寂しい情景が、詩人の忸怩たる思いとともに読者の心に染み渡ってきます。