 トップページ
トップページ ×
×
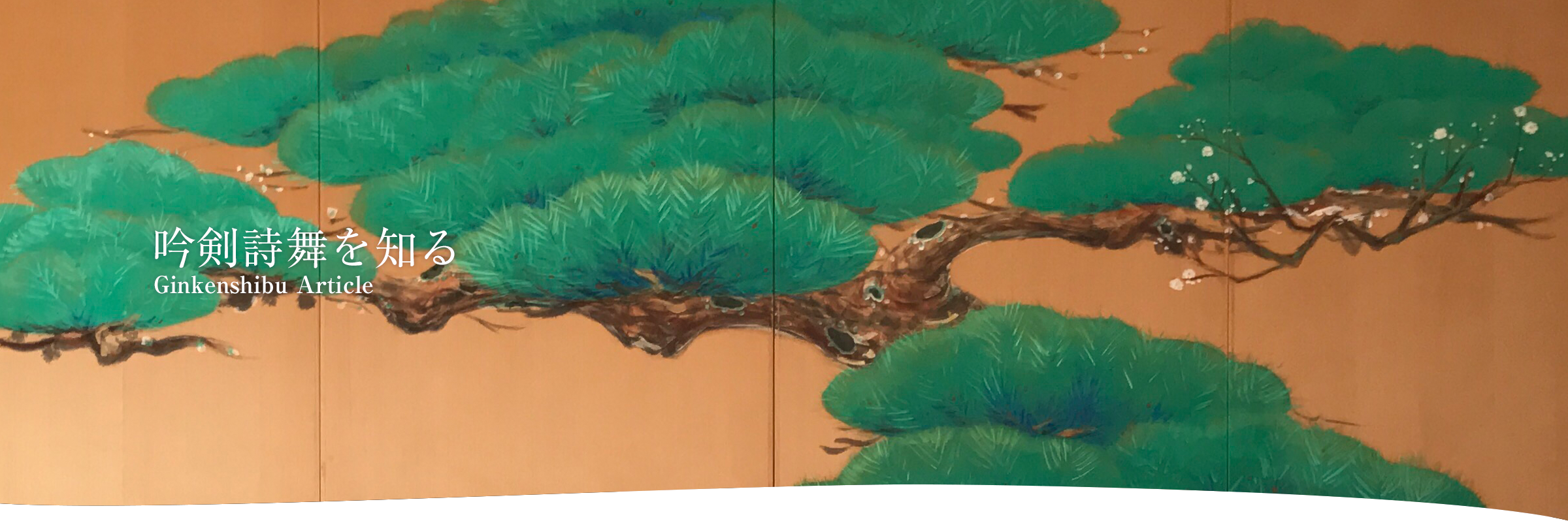

張籍「秋思」
(ちょうせき「しゅうし」)
「秋思」とは、秋のもの思い、秋のもの寂しい気持ち、という意味です。秋はさびしいもの、悲しいもの、という自覚が中国の文学に登場するのは、紀元前の戦国時代、宋玉の「九弁」です。文学上「楚辞」と言われる作品群の一つです。「楚辞」は「兮」という助字が句中や句末に使われます。
悲哉秋之爲氣也[悲しい哉秋の気為るや]
蕭瑟兮草木搖落而変衰[蕭瑟として草木搖落して変衰す]
憭慄兮若在遠行[憭慄として遠行に在りて]
登山臨水兮送將歸[山に登り水に臨んで将に帰らんとするを送るが若し]
〈秋の気は、何とも悲しく、草木がわびしく枯れ落ち、うらぶれる。心が冷えびえとするのは、遠い旅の空のもと、山に登り水に臨み、故郷に帰る人を見送るときのよう。〉
ものの哀れを感じる秋という「悲秋」の語は、この作品から生まれました。秋の寂しさ・悲しさは、旅の空のもとでの別れの寂しさ・悲しさに似ている、という感覚は、のちの文学にも引き継がれていきます。中国では漢詩文を作る人は役人・政治家で、都に滞在したり、あるいは左遷されたり、命令によって出張したりと、多く故郷を離れていました。つねに「客」=旅人という感覚をいだいていました。「旅」は「悲秋」を詠うのに最も適していて、「旅」にあれば、心はいっそう敏感になり、ちょっとした「風」の音や気配によって、秋の到来を感じます。劉禹錫は「秋風引」(秋風の引)で、秋風を真っ先に聞くのは旅人であると言います。
何處秋風至[何処よりか秋風至る]
蕭蕭送雁群[蕭蕭として雁群を送る]
朝來入庭樹[朝来庭樹に入るを]
孤客最先聞[孤客最も先んじて聞く]
〈どこからか秋風が吹き始め、さびしげに雁の群れを送ってくる。朝がた庭の木の枝葉をざわつかせる音を、孤客の私がもっとも先に聞きつけた。〉
藤原敏行の和歌、秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬるも、秋の訪れを風の音から感じ取っています。
さて、張籍の「秋思」は、風によって秋を感じ、故郷を離れている寂しさから、なつかしい家族に手紙を書きます。
洛陽城裏見秋風[洛陽城裏秋風を見る]
欲作家書意萬重[家書を作らんと欲して意万重]
復恐匆匆説不盡[復た恐る 匆々説き尽くさざるを]
行人臨發又開封[行人発するに臨んで又封を開く]
〈洛陽の町に秋風が吹きはじめ、木の葉の翻るのが見える。故郷が恋しくなり、家へ手紙を書こうと思うが、次から次へと思いがわいてくる。慌てて書いたので、書き落としがないかと心配になり、言づてをする旅人が出発するとき、もう一度封を開いて見た。〉
「行人」は旅人です。当時は手紙を集配する郵便制度はありませんでしたので、受取人の地方へ行く旅人に手紙を託し、届けてもらっていました。積もる思いに、書き残しはないかと心配になり、出発直前にまた封を開いて確かめる、という気持ち、よく分かります。詩では「秋風を聞いた」と言わずに、「秋風を見た」と言います。風によって木々の葉がそよぎ、散るさまを見て、「秋風を見た」と言うのです。視覚をとおして風が描かれますが、そこには風の音も、風の肌にふれる感じもともなっています。秋風によってまず「悲秋」が詠われ、それによって故郷へ手紙を書くという「秋の思い」が重ねられ、書き残しを心配するというさらなる「秋の思い」が重ねられます。
秋風が吹くと故郷が恋しくなるという有名な張翰の故事もあります。張翰は西晋の人で、洛陽で宮仕えをしていましたが、ある年秋風が吹き始めると、故郷の呉(蘇州)の蓴菜のあつものと鱸魚のなますが恋しくなり、官職を捨てて帰ったといいます。姓が同じ「張」の張籍も、呉の人です。
先に挙げた劉禹錫にも「秋思」という詩があります。秋は寂しいと人は言うが、私は、秋の日はかえって春の朝に勝っている、と従来の秋のとらえ方に異を唱えます。日本では、菅原道真の「秋思の詩」がよく知られています。中国の伝統を踏まえた、秋の悲しい詩です。いつか読み解く機会があると思います。