 トップページ
トップページ ×
×
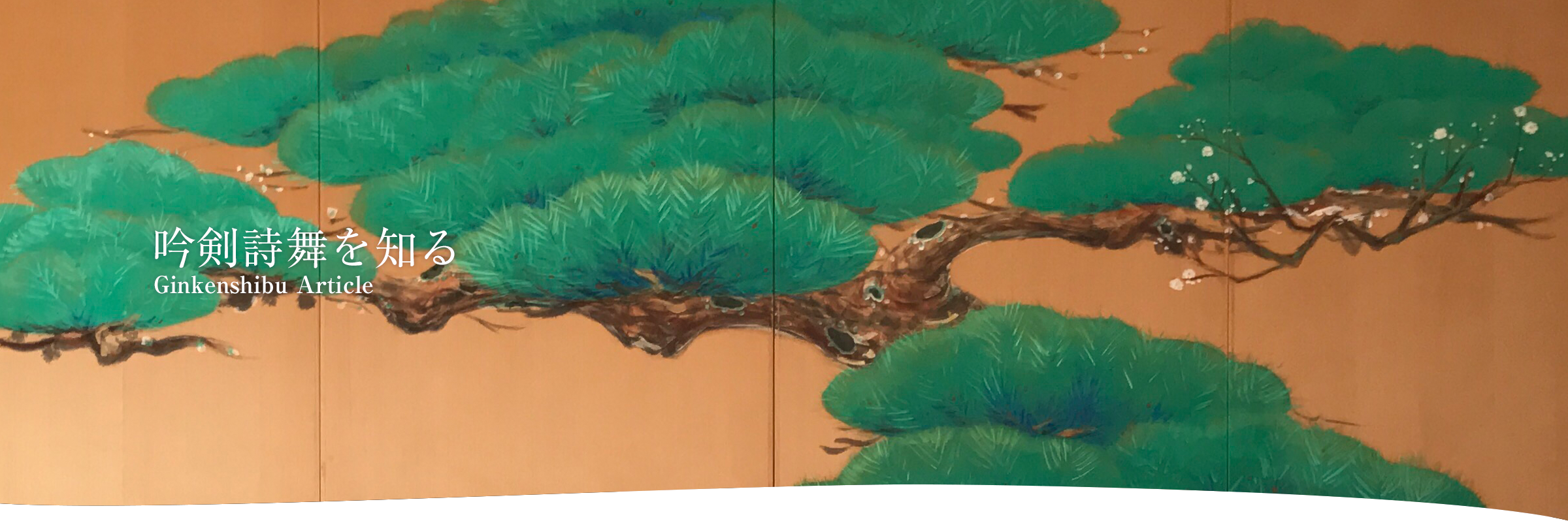


〈説明〉
講習会で「2音節1拍」の話をしたとき、時間切れで、最後に一言、「『ン』に関する例外もありますが・・・・・」程度の説明で終わってしまった記憶があります。一般的には「ン」だけで1音節の扱いとしますが、元来、助動詞以外の「ン」は漢字の読みとしての「ン」であり1音ではなりたたず、必ず直前の音と一体となって成り立つ音です。
「ちゃ・ちゅ・ちょ」などの拗音において「ゃ・ゅ・ょ」などが1音では成り立たず「チ」と一組で1音節の扱いになっているのと似たような存在です。「似たような」という点が肝心です。つまり全く同じ扱いというわけではありません。しかし「ン」はほかの音節と異なり、「ン」から始まる言葉がありません。そのために「ン」の個所が拍子の表になると「気持ち悪い」のは確かです。「2音節で1拍子」を提唱するのは、その読み方が調子よく、気持ちが良いからなのです。そのため昔から日本語の読みがこのスタイルで行われてきたのです。ですから「2音節で1拍子」を守らんがため、無理やり気持ち悪い読みを選ぶのは本末転倒です。昔から行われてきた調子のよい読み方を振り返って検証してみたら「2音節で1拍子」だったということであり、規則として設けられたことではありません。「古今の」の「コン」を詰めればよいというのは、詰めることによって「コン」が2音節ではなく「コン」が1音節の感じに近くなるので「ココン」が2音節で「ココン ノ」が調子よく聞こえるのです。「チヤ」なら2音節ですが、これを詰めて発音すれば「チャ」となって1音節に聞こえるのと似たようなことです。
参考までに紹介します。リズムを重視する英語圏では、「in」「an」「ten」「pen」などは音節として数えます。ご質問の「古今の」と同じような同じようなことですぐ思い起こされる言葉に「狐鞍」「遺恨」「他人の」「無くんば」「期せん」「知らん」「児孫の」「美田を」「墓前に」などありますが、この中で二つだけ「〇ン」を詰めない方がよいものがあります。「期せん」「知らん」がそれです。この時の「ん」は助動詞ですので、前の音と一組になっているわけではありません。ですからことさらに詰めると「期せん」が「機先」のように聞こえてしまう恐れがあります。この点を意識しましょう。逆に、詰めないと具合が悪いのは剣舞の伴吟をする時です。「イコ ン」「タニ ンノ」「ナク ンバ」「ジソ ンノ」「ビデ ンヲ」という読みで吟じると舞手はきっと「力が入らず舞いにくい」と言うでしょう。私が「2音節1拍」を提唱するのは、最近4音節の言葉が「2・2」ではなく「3・1」と読む人が増えていることがとても気になるからです。「2音節1拍」の「ン」に関する例外についての説明をしてきましたが、そもそも「2音節1拍」とは何の話?とお思いの方のため、あらためてご説明いたします。
元来詩吟は、詩句の部分には節を用いず、詩句と詩句の間に節をつけて歌うものとして続いてきましたので、基本音階に基づいた発声でありながら詩句の部分は朗読に基づいています。コンクールで胸中後のアクセントを規定に盛り込むことが出来るのも、詩吟の「読み」の部分が朗読に基づいているからです。日本語の詩文を朗読するとき、自然と「2音節1拍」のリズムで朗読しているのですが、近年、詩吟における読みが、このリズムで行われない傾向が出てきています。最も目立つのは、4音節の言葉で、音節目が「て・に・を・は」などの接続詞となっている場合の読みです。例えば「一枝を・・・」や「万株の・・・」などは本来「イッ シヲ・・・」「バン シュノ・・・」と読むのが普通なのですが、素読の時にはこのように読む人でも、吟じる時は「イッシー ヲ・・・」「バンシュー ノ・・・」と読むことが多いのです。特に音程の高い節に多く聞かれます。読みのリズムとしてはとても調子の悪い読みです。
30年度のコンクール課題吟より、心配な詩句を挙げてみました。
落つるの・郊墟に・一夢の・一枝を・万株の・枕を・処に・旧時の・半夜の・恩賜の・登るは・書生の・千樹の・多しと・出ずれば・薪を・敗荷は・耐うるは・煙雨の・「エンウー ノ・・・」とならないように気を付けましょう。
以前、FM収録の時、吟じている吟者に対して調整室で待機中の吟詠家が「3・1で吟じた!」と指摘なさったことがありました。まさに私が日頃気にしていることをおっしゃたので、驚きました。「2音節1拍」の話はなかなか浸透しないなと思っていましたので。驚いたと同時に「覚えてくださっている方もあるのだ」とうれしくもなりました。しかし同時に不安も覚えました。「2音節1拍」の話が吟界に十分浸透すると、またぞろこれが独り歩きするのでは?!という心配です。鼻濁音の注意喚起がいつの間にかコンクールの規定に盛り込まれ、減点の対象となったように、一義的にマニュアル化されると、条件の違いによる例外も考慮されずに権威のみ膨らむことがないだろうかと・・・。
全ての事柄が吟詠芸術向上のためでなくてはならないということを常に念頭に置いておきたいものです。