 トップページ
トップページ ×
×
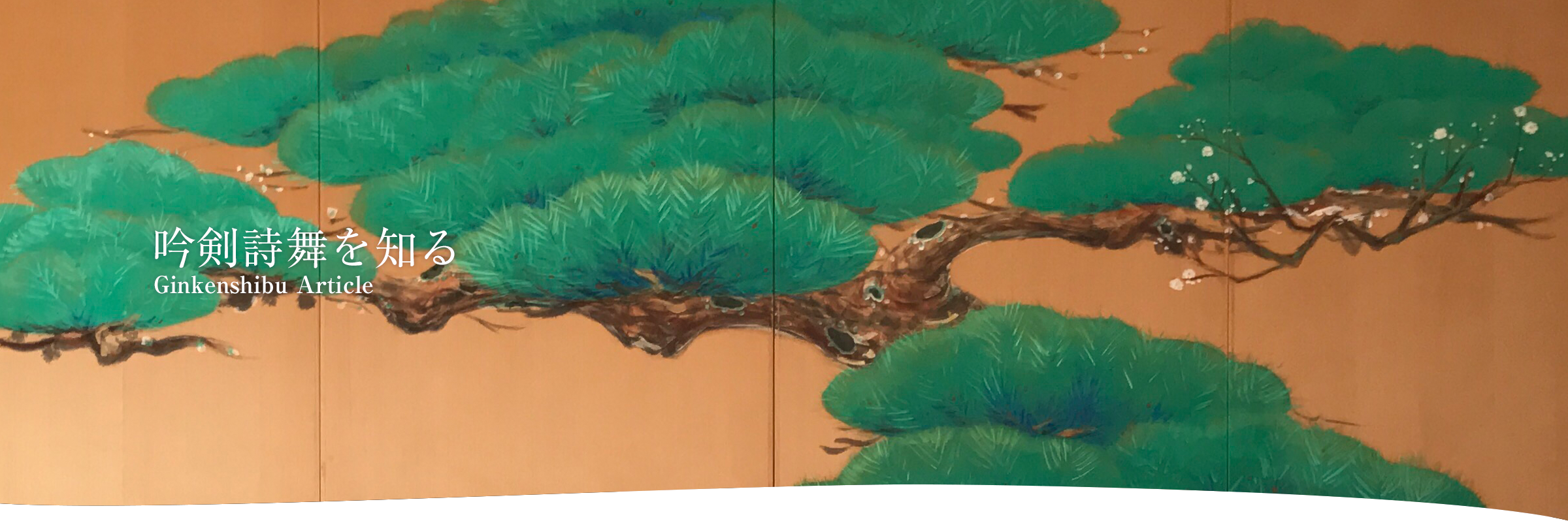

良寛「余生」
(りょうかん「よせい」)
良寛は、越後(新潟県)出雲崎の町名主橘屋山本家の長男として宝暦八(一七五八)年に生まれました。江戸時代の後期、封建政治がいたるところで綻びはじめ、人々の苦しみが増えてゆく時代で、橘屋も新興勢力に押されてしだいに衰えてゆきます。良寛は十八歳のころ、理由はよく分かりませんが、隣町の尼瀬の光照寺で剃髪しました。二十二歳のとき来錫した国仙和尚に従って得度し、備中玉島の円通寺に行き修行しました。三十三歳、国仙から印可の偈を授けられ、その後諸国を行脚し、三十九歳越後に帰郷、四十歳国上山の五合庵に入り、四十八歳から六十歳まで定住しました。この「余生」は、五合庵に入り、隠棲生活を始めたころの作品とされています。
雨晴雲晴氣復晴[雨晴れ雲晴れて気も復た晴る]
心淸遍界物皆淸[心清ければ遍界物皆清し]
捐身棄世爲閑人[身を捐て世を棄てて閑人と為り]
初月與花送餘生[初めて月と花とに余生を送る]
〈雨がやみ雲が去り、大気も晴れわたった。心が清々しいと世の中の物もみな清々しく感じられる。自分の身も浮き世も棄てて「閑人」となり、こうして初めて月と花とを相手に余生を送るのだ〉。
「遍界」は遍き世界、世の中をいいます。「閑人」は「閑者」また「間者」とするテキストもあります。「閑人」は「閑客」ともいいますが、漢詩には「閑者」また「間者」の語はあまり見かけません。ちなみに「間者」は日本語で、スパイの意です。「余生」は残された命。
前半は、心を曇らせる外界のモノがなくなることによって、心が清らかになり、それによって外界のモノがすべて清らかに感じられる、と言います。後半は前半を承けて、心を曇らせる我が身や浮き世という外界のモノをみずから捨てて、心清らかな「閑人」となった、だから清らかな月や花とともにこれからの余生を送ろう、と言います。
前半はよく経験することで分かりやすいのですが、後半は理屈としてはわかりますが、実際に行うことは難しいです。俗に染まった我が身も浮き世も捨てて「閑人」になることは、凡人にはとうていできません。「閑人」は辞書で引くと「ひま人」「無用な人」とありますが、表面的な意味で片付けられるものではありません。自分の身さえも捨て、世も捨てるのですから、「無一物」で「無欲」で「純粋無垢」でなければなりません。良寛のいう「閑人」となって、初めて月や花という、清らかな自然と一体になれるのです。
良寛の詩に、乞食のあと月を眺め花に迷った、と詠う五言律詩があります。その頷聯と頸聯。
食はわずかに路辺に乞ひ、家はまことに蒿萊に委ぬ。
月を看て永夜に嘯き、花に迷うて帰るを知らず。
「蒿萊」は荒草です。良寛は子供たちとよく遊びました。純粋な心をもった「閑人」だからこそできたのです。
霞たつながき春日をこどもらと手まりつきつゝこの日暮らしつ
五合庵のある国上山は越後平野の中ほど、海よりに立つ山です。その中腹に真言宗の国上寺があり、五合庵はその住職の隠居所でした。良寛はそれを借りて住んだのですが、五合庵は万元和尚によって貞享(一六八四~一六八八)の末、または正徳年間(一七一一~一七一六)に建てられたといいます。万元は旧い庵を修理し、一日に五合の米を布施米として支給されたので庵の名にしたといいます。
良寛の住んだ五合庵には家財道具などはもちろんなく、釜のなかに埃がたまることもあり、かまどに煙が立たないこともあったといいます。このような所にも夜泥棒が入り、何も盗るものがないので着て寝ている着物を盗ろうとしたので、良寛は知らないふりをして寝がえりをうち、盗りやすいようにしてやったという逸話があります(着物ではなく布団という話もあります)。その時の句でしょうか。
盗人にとり残されし窓の月
良寛は、和歌・俳句・漢詩・漢文のすべてに精通し、それを書いている筆の文字も魅力的です。心温まる逸話も多く残っています。